社内システムは、企業活動の効率化や生産性向上に不可欠なツールです。しかし、せっかく導入したシステムも、適切に運用されなければその効果を十分に発揮できません。特に、システムを使いこなすための社内マニュアルの運用は、システムの有効活用に直結する重要な要素といえます。ところが、多くの企業で社内マニュアルの運用に課題を抱えているのが現状です。
こちらでは、社内システムのマニュアル運用における主要な課題を改めて整理し、具体的な課題解決策、そして継続的な改善のための方法について解説します。
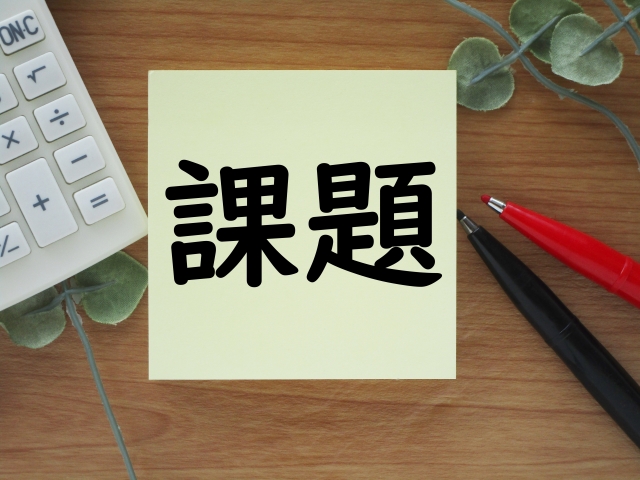
社内システムのマニュアル運用においては、多くの企業がさまざまな課題に直面しています。主な課題として、以下の3つが挙げられます。
社内システムのマニュアルは、必要なときにすぐに見つからなければ意味がありません。しかし実際には、マニュアルがどこにあるのかわからなかったり、探し出すのに時間がかかったりするなど、アクセス性の問題が多く発生しています。
例えば、以下のような課題が考えられます。
キーワード検索ができない、検索精度が低い
目的の情報にたどり着くまでに多くのページを遷移する必要がある、目次がない
マニュアルが複数の場所に分散して保管されている、ファイルサーバーのディレクトリ構成が複雑
これらの課題により、従業員は必要な情報にアクセスするのに苦労し、業務効率の低下につながることがあります。
社内システムは、定期的にアップデートされることが一般的です。そのため、マニュアルの内容も最新の状態に保つ必要があります。
しかし実際には、更新が滞って古い情報が放置され、誤った操作を招いたり、システムトラブルの原因になったりするケースが少なくありません。
更新が滞る原因としては、更新作業の担当者が不明確、更新のためのワークフローが確立されていない、などが考えられます。
わかりやすいマニュアルを作成しても、システム自体が使いにくい場合は、システムの利用促進につながらない可能性があります。
例えば、UI/UXがわかりにくい、操作方法が複雑、エラーメッセージがわかりにくいなどの問題があると、従業員はシステムの利用に抵抗を感じてしまいます。
このような場合は、マニュアルだけでなく、システム自体の改善も必要になります。

社内システムのマニュアル運用において、情報へのアクセス性、情報鮮度維持、システムの使いにくさに関する具体的な課題解決策を以下に示します。
目的の情報にアクセスしづらいという課題に対し、以下の対策が有効です。
マニュアル内の検索機能を強化することで、利用者は必要な情報を迅速に見つけることができます。キーワード検索に加え、関連語や類義語検索、あいまい検索にも対応することで、検索精度を向上させます。
よくある質問と回答をまとめたFAQシステムを導入することで、利用者は疑問点を手軽に検索し、自己解決を図ることが可能になります。これにより、ヘルプデスクへの問い合わせ件数を削減し、対応負荷を軽減できます。
利用者の視点に立ったわかりやすい目次や索引を作成し、マニュアル構成を見直します。図表や動画を効果的に活用することで、視覚的な理解を促進し、目的の情報へのアクセス性を高めます。
情報の更新が滞り、古い情報が放置されるという課題に対し、以下の対策が有効です。
明確な更新手順を定めたワークフローを確立することで、更新作業の抜け漏れや遅延を防ぎます。更新履歴を記録し、誰がいつどの情報を更新したかを追跡可能にすることで、情報の信頼性を確保します。
システムや業務内容に精通した担当者を更新責任者に指名し、情報の正確性を維持します。担当者には定期的な研修を実施し、常に最新の知識を習得させ、高品質なマニュアルを提供します。
システムの変更や機能追加の頻度に合わせて、マニュアルの更新頻度を定めます。定期的な更新を徹底することで、常に最新の情報が利用可能になり、利用者の混乱やミスを未然に防ぎます。
マニュアルを読んでもシステムが使いにくいという課題に対し、以下の対策が有効です。
ユーザーテストに基づく改善で直感的な操作を実現し、利用者の学習コストを軽減します。
主要操作手順を動画で解説し、視覚的に理解を深め、操作習熟度を向上させます。
新入社員やシステム変更時に研修を実施し、効果的なシステム活用を促進します。
社内システムのマニュアル運用を改善するためには、PDCAサイクルを回すことが重要です。PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのステップを繰り返すことで、継続的な改善を図る手法です。それぞれのステップで何を行うか、詳しく見ていきましょう。
まずは現状のマニュアル運用における課題を明確化します。情報へのアクセス性、情報の鮮度、システム利用の促進といった観点から、具体的な問題点を洗い出しましょう。例えば、「目的の情報にたどり着くまでに時間がかかる」「古い情報が放置されている」「マニュアルを読んでもシステムを使いこなせない」といった課題が考えられます。
次に、具体的な数値目標を設定します。「検索時間○○%短縮」「マニュアル更新頻度を週○回にする」「システム利用率○○%向上」といった目標を設定することで、改善効果を測定しやすくなります。
計画に基づき、具体的な施策を実行します。例えば、検索機能の強化、更新ワークフローの確立、操作動画の作成などが挙げられます。実行段階では、計画通りに進んでいるかこまめに確認することが重要です。
実施した施策の効果を測定し、目標に対してどれくらい達成できたかを評価します。「検索時間は何%短縮されたか」「マニュアルは計画通り更新されているか」「システム利用率は何%向上したか」などを具体的な数値で確認します。達成度が低い場合は、その原因を分析します。
評価結果に基づいて、改善策を検討・実施します。例えば、検索キーワードの追加、更新手順の見直し、操作動画の内容改善などが挙げられます。うまくいった施策は標準化し、次のPDCAサイクルにつなげます。
PDCAサイクルを効果的に回すためには、各ステップで具体的な数値目標を設定し、定期的に見直し改善していくことが重要です。また、関係者間で情報を共有し、協力して進めることも成功の鍵となります。これらのポイントを踏まえ、PDCAサイクルを継続的に回すことで社内マニュアル運用を改善し、業務効率の向上へとつなげましょう。
社内システムのマニュアル改善は、従業員の満足度向上、ひいては生産性向上に直結する重要な取り組みです。
効果的なマニュアル改善を行うための流れを以下に示します。
まず、既存のマニュアルの課題を明確にします。従業員へのアンケートやヒアリング、問い合わせ内容の分析などを通じて、マニュアルの使いにくさや情報不足の箇所を洗い出します。
例えば、「検索機能が使いにくい」「情報が古くなっている」「必要な情報が見つからない」といった課題が挙げられます。
現状分析をもとに、具体的な目標を設定します。例えば、「マニュアル利用率の向上」「問い合わせ対応時間の短縮」「従業員満足度の向上」などが挙げられます。
目標は、具体的かつ測定可能なものにすることで、改善の効果を客観的に評価できます。
明確になった課題と目標を踏まえ、具体的な改善策を実施します。例えば、検索機能の改善、情報のアップデート、わかりやすい図表の追加などが挙げられます。
改善策実施後はその効果を測定し、必要に応じてさらなる改善を行います。効果測定には、アクセスログ分析やアンケート調査などが有効です。
また、従業員からのフィードバックを収集し、継続的な改善につなげることも重要です。
WEBふきだしは、社内システムのマニュアル運用における課題を素早く解決できるツールです。画面上に直接ガイドを表示できるため、利用者が迷わずに操作することができます。お使いのシステムを修正せずに導入可能で、100人以下であれば無料でご利用いただけます。ぜひお試しください。
| 事業者名 | WEBふきだし合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川1-19-9 401号 |
| TEL | 03-6260-1508 |
| メール | support@fukidashi.site |
| URL | https://fukidashi.site/ |